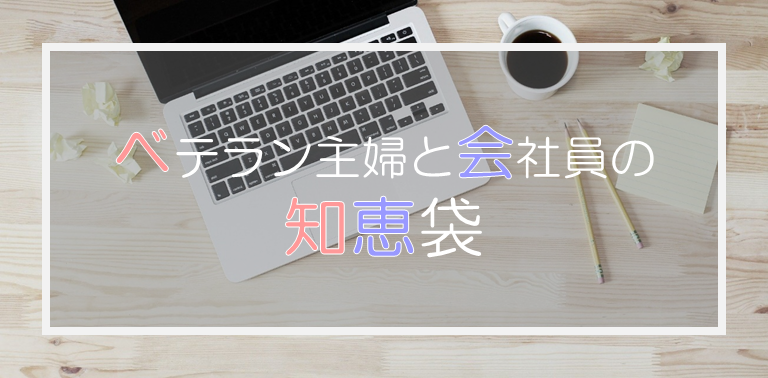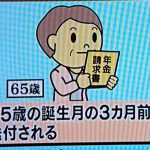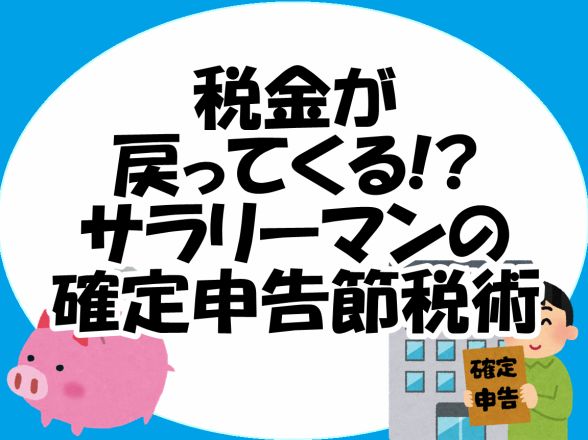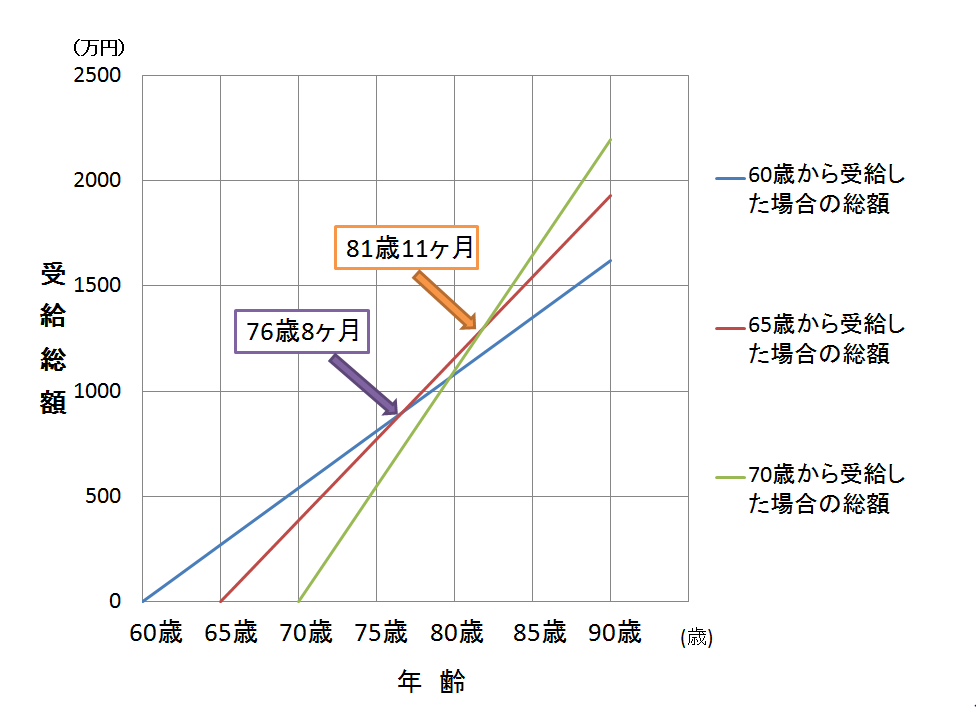
老齢基礎年金の受給開始年齢は、
原則65歳からですが、
本来よりも早く受け取る
「繰り上げ受給」と、
受給開始を遅らせる
「繰り下げ受給」という制度があります。
この記事では、
個々人の状況によって
年金の繰り上げと繰り下げ、
受給額はどれくらい違うのか、を
より具体的にわかりやすくお伝えします。
家電・家具のお届けレンタルサービス「かして!どっとこむ」のプログラムです。
業界トップのシェアと実績を誇るサービスで、年間通じて需要が安定しているのが特長です。
年金は一度繰り上げたら変更できません
繰り上げは
最大で5年間前倒しができ、
60歳以降の1ヶ月単位で
受給開始期間を指定できます。
でも、本来よりも早くから
年金をもらうわけですから、
満額を受け取ることはできません。
1ヶ月繰り上げるごとに
0.5%ずつ減額されます。
60歳から年金を受け取る場合、
減額率は、
30%(0.5%×60ヶ月)になってしまいます。
それと、
知っておいていただきたいのは、
一度繰り上げると
途中で変更はできず、
減額された年金を生涯、
受け取ることになることです。
![]()
17年間、お金の研究を続けたファイナンシャルアカデミーが2019年に新設した講座
実際に1億円の資産を築いた「富裕層」研究から抽出した黄金ルールと、
参加者各個人が自分のロードマップが描けるまでの知識を2.5時間で得られる講座です。
主に30〜40代をターゲットとした内容で、貯蓄や節約より資産を増やしたい人向けです。
年金の繰り上げ受給の注意点とは
減額に加え、
繰り上げには次のような注意点があります。
①繰り上げ請求を行うと、
障害者年金、寡婦年金は原則として受けられない。
②国民健康保険の任意加入、追納ができない
③65歳になるまでは、繰り上げ支給の年金か、
遺族基礎年金のいずれか一方しか受けられない
④加給年金や振替加算は繰り上げ受給ができず、
本来の受給開始年齢から支給される
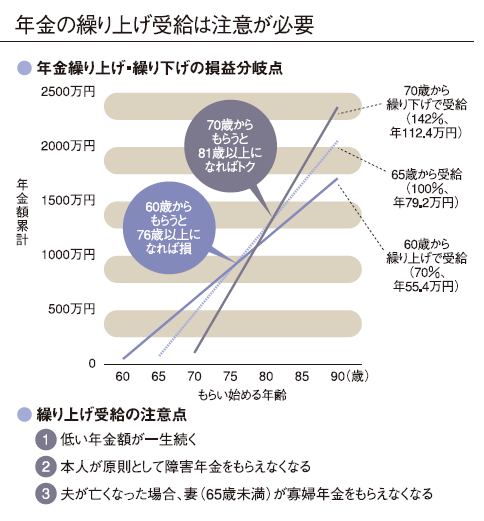
年金で長生きすると「繰り上げは損」って?
繰り下げ受給も同様に、
最長で5年、66歳から1ヶ月単位で
受給開始を遅らせられます。
繰り下げをすると、
1ヶ月ごとに支給額が0.7%増額され、
5年繰り下げて
70歳から受給開始した場合は、
42%も増額された年金を、
生涯受け取れる計算です。
![]()
▼手数料が業界最安値水準!
現物最低50円(税抜)~、信用最低0円(税抜)~!
▼口座開設費が0円
その他口座管理・維持費、入金手数料※、出金手数料も0円
※クイック入金をご利用いただいた場合
▼充実の取引ツール・アプリ
初心者からプロまでさまざまなスタイルに対応した取引ツールを無料で取り揃えています。
▼NISA(少額投資非課税制度)口座にも対応
しかし、繰り下げについても以下の注意点があります。
①65歳を過ぎて繰り下げ待機中に死亡した場合、
65歳から死亡した月までの分が
「未支給年金」として遺族に支払われる。
②加給年金や振替加算は繰り下げが出来ないうえ、
繰り下げ待機中はいずれも支給されない。
③繰り下げ待機中に遺族年金などの権利が発生した場合、
その月に繰り下げの請求をするか、
さかのぼって65歳から受給かを選択できる。
年金の繰り上げ・繰り下げの分岐点とは
結局のところ、
繰り上げや繰り下げをした場合に、
受給総額は
”何歳まで生きるか” によることなります。
繰り上げの場合
繰り上げの場合、
繰り上げた年齢よりも
16年8ヶ月以上長生きすると、
受給総額が通常受給を下回ります。
繰り下げの場合
逆に繰り下げの場合は
長生きするほど有利で
繰り下げた年齢よりも
11年11ヶ月長生きすると、
受給総額が通常受給を上回ります。
一度繰り上げや繰り下げの請求をすると
後で取り消しはできず、
支給率も生涯変わりません。
それぞれのメリットとデメリットを
よく理解したうえで、慎重に判断してください。
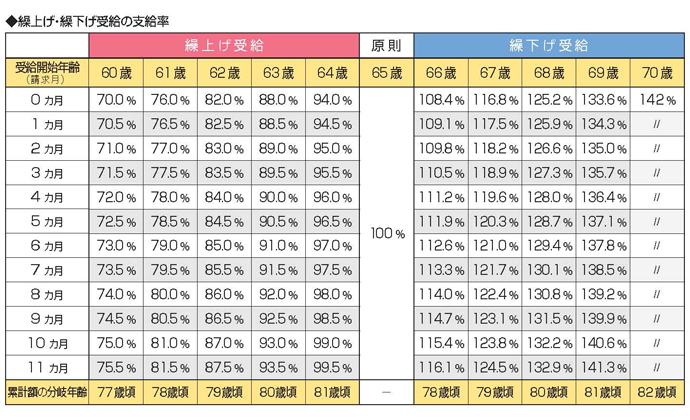
繰り上げの減額率と繰り下げの増額率
65歳から支給される老齢基礎年金:780,100円
(2016年度 満額を基準に)
繰り上げの減額分(1ヶ月ごとに0.5%減額)
60歳:546,070円(▲30%)
61歳:592,876円(▲24%)
62歳:639,682円(▲18%)
63歳:686,488円(▲12%)
64歳:733,294円(▲6%)
損益分岐点(繰り上げも繰り下げもしない)
65歳:780,100円(0%)
繰り下げの増額分(1ヶ月ごとに0.7%増額)
66歳:845,628円(8.4%)
67歳:911,157円(16.8%)
68歳:976,685円(25.2%)
69歳:1,042,214円(33.6%)
70歳:1,107,742円(42.0%)
一度、きちんとご確認ください!
![]()
17年間、お金の研究を続けたファイナンシャルアカデミーが2019年に新設した講座
実際に1億円の資産を築いた「富裕層」研究から抽出した黄金ルールと、
参加者各個人が自分のロードマップが描けるまでの知識を2.5時間で得られる講座です。
主に30〜40代をターゲットとした内容で、貯蓄や節約より資産を増やしたい人向けです。
最後に
僕もあと数年で
定年退職を迎える予定です。
年金の「繰り上げ」「繰り下げ」は
定年後の最重要課題であると考えています。
どちらがいいのかは、
その時の個々人の状況にもよりますが、
僕の場合も、正直、
その時になってみないと
判断できないと思います。
できれば、
65歳までは働きたいと考えています。
でも、ひとつだけ思うのは、
長生きすると繰り上げは損、
繰り下げは得になるとは言いますが、
人はいつまで生きれるのかは、
誰にもわかりません。
70歳までの繰り下げは、
老齢基礎年金 780,100円の142%の
1,107,742円を生涯もらえるというのは、
正直すっごく魅力ですが、
それまでに死んでしまうかもしれません。
遺族配偶者にはいいのかもしれませんが・・・。
僕もそこまで
長生きする自信がありません:^^;
いずれにしても、
僕は1961年生まれですが、
どの選択がいいのかは、
今はあまりわかりません。
でも、それまでに情報と知識を蓄積して、
その時になって、自分に一番有利な選択はどれなのかを
学習しながら、ベストな選択ができればと思っています。
![]()
DMMコミックレンタルは業界最安級の1冊95円からの宅配レンタルサービスです!
取り扱いタイトルは1.6万以上あり、不朽の名作から最新の話題作まで豊富にあります。
電子書籍で購入するより、マンガ喫茶に行くより、お得にマンガが読めるサービスです。
![]()
帰宅後、靴にシュッとするだけで翌朝すっきりニオイケア
独自処方の天然パウダーがニオイ菌を除菌・消臭、革靴・運動靴等全ての靴で使用可能です!
◆こんな記事も読まれています
コンビニで消化の良い食べ物を7つ!買うならこれがオススメ!!
税務署へ相談電話するメリットとデメリット!でも、したほうがいい3つの理由
宅配便をコンビニで発送!その料金と正しいやり方を伝授します!!
【知らないと損】年金の損をしないもらい方!加給年金、繰り下げ年金(若い人も必見!)
不妊治療の費用は医療費控除で戻ります!その申請方法と返還金額はいくらなの!
加給年金と振替加算の違い!加給年金の対象条件と加算内容とは?
サラリーマンの節税!所得控除で税金を安くする仕組みを伝授!!
個人事業者が経費で落とす!確定申告で自宅の家賃やキャバクラ代さえも??
医療費控除の留意ポイント!10万円以下でも控除が受けられる方法とは??
遺族年金をもらうための条件は?妻が夫と離婚や死別した場合にもらえる金額は??
![]()
ゲーム買取のグッズキングです。
本体やソフト、周辺機器からレトロゲーム含めて高価買取しております
![]()
DMMコミックレンタルは業界最安級の1冊95円からの宅配レンタルサービスです!
取り扱いタイトルは1.6万以上あり、不朽の名作から最新の話題作まで豊富にあります。
電子書籍で購入するより、マンガ喫茶に行くより、お得にマンガが読めるサービスです。
![]()
1 180,000本以上の動画が見放題、最新レンタル作品もぞくぞく配信
2 動画だけでなく、電子書籍も1つのアプリで楽しめる、マンガ、ラノベ、書籍、雑誌など豊富なラインナップ
3 毎月1,200円分のポイントが貰える
最新作の視聴や書籍の購入に利用可能
◆31日間無料トライアルの特典◆
1 見放題作品が31日間無料で視聴可能、最新作はレンタル配信(個別課金)となります。
2 600円分のポイントプレゼント:DVD・ブルーレイよりも先行配信の最新作、放送中ドラマの視聴や
最新コミックの購入に使用可能。
3 追加料金なく、80誌以上の雑誌が読み放題